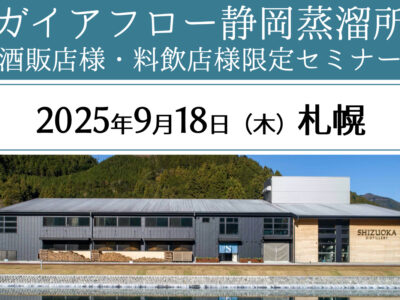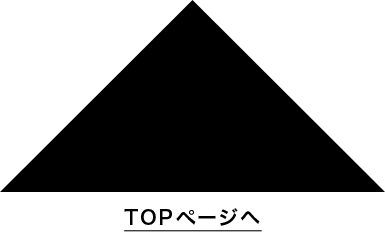静岡蒸溜所は、この度発表された東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2025(TWSC 2025)にて、「ベストディスティラリー賞 SDGs部門」を受賞いたしました!
TWSCは、国内最大規模を誇るウイスキーとスピリッツの審査会です。
その中で「ベストディスティラリー賞」は、品質だけでなく、蒸溜所の取り組み全体を評価する特別賞として位置づけられており、SDGs部門は、持続可能性や地域社会との関わりを重視した取り組みを対象に選出されます。
「ベストディスティラリー賞 SDGs部門」受賞によせて
この度はベストディスティラリー賞に、静岡蒸溜所をお選びいただき、ありがとうございます。
ガイアフローは2012年、再生可能エネルギーを一般家庭に届けることを事業の目的として設立した会社でした。元々、私が再生可能エネルギーの普及に強い関心を持ち、事例研究を何年も行っていました。東日本大震災が来て、社会が急速に動き始めたため、切なる必要性を感じて会社設立に至った次第です。
残念ながら、会社設立後に規制緩和が大幅に遅れ、その事業は実現しませんでした。代わって、クラフトウイスキー製造の事業化を思い立ち、ガイアフローはウイスキーの会社になりました。
そのようなベースがあって、静岡蒸溜所はその構想段階から「サステナビリティ」をコンセプトのコアに企画立案しています。地元大麦も、地元杉の発酵槽も、地元の薪の直火も、地元のミズナラ樽も、全てはその流れの一部です。
2015年になって国連で提唱されたSDGs(持続可能な開発)という言葉は、他国ではほとんど使われていないため、弊社では使っておりませんが、個々の取り組みにおいては通じるものがあるかもしれません。
10年前には業界で異端であった弊社の取り組みが、日本国内のみならず本場スコットランドでも採用される時代になったことが、このように評価していただけた理由かと思います。
ガイアフロー静岡蒸溜所は、目指す世界の実現に向けて、これからも進んでまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。
ガイアフロー静岡蒸溜所
代表 中村大航
静岡蒸溜所では、2012年のガイアフロー創業当初から「この土地だからこそできるウイスキー」を目指し、地域の資源と共に歩んできました。
そのような取り組みを「SDGs17の目標」に当てはめてご紹介します。
県内の生産者、自治体と連携した静岡県産大麦の栽培・使用


SDGs目標2:飢餓をゼロに
地元農業との連携による持続可能な農業の促進
生産者、JAや自治体の方々と協働し、米づくりの裏作として大麦の栽培をしています。
これにより、生産者の方々に新たな収入機会も創出。地域の農業を支えていくという、ウイスキー業界として新しい試みでもあります。

SDGs目標12:つくる責任 つかう責任
輸入依存から脱却、地元産原料を活用した持続可能な生産モデルを構築
輸入原料に頼る従来の製法から、国産原料、特に地元産の原料にこだわった、より「ジャパニーズウイスキー」らしいウイスキーづくりという革新的な製法を確立しました。
日本のウイスキー業界に「テロワール」の概念を導入した画期的な試みといえるでしょう。

SDGs目標15:陸の豊かさも守ろう
地域の耕作地の活用と土壌保全への貢献
静岡県ではこれまで、ほとんど大麦を栽培していませんでした。
蒸溜用大麦の栽培という新たな農業の可能性を見出すことで、持続可能な土地利用が促進され、生物多様性の維持や景観保全にも寄与しています。
関連する記事はこちら
森林資源を活かした薪直火蒸留

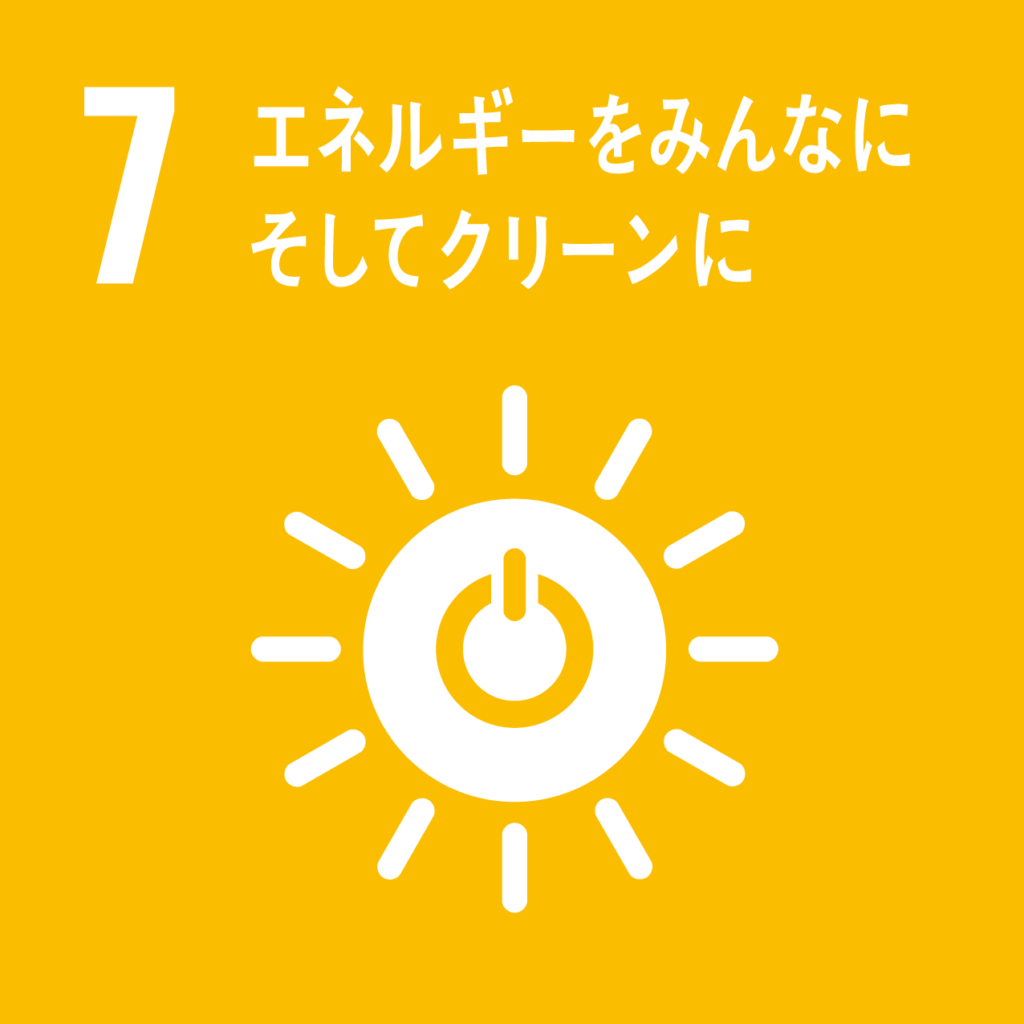
SDGs目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに
化石燃料だけに頼らず、地域資源である薪を利用
輸入した石油・石炭・天然ガスだけに依存せず、地元の間伐材を熱源として蒸留工程を行っています。
静岡の森で得られる間伐材を、地元の森林事業者と手を組み、薪割りして資源化しています。通常は「行き場のない資材」として埋もれてしまう針葉樹の間伐材ですが、静岡蒸溜所では数年にわたる研究の末、熱源として十二分に活用することができています。

SDGs目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう
地域の知と技術を結集した、ウイスキーづくりの革新
薪直火蒸留機Wは、ウイスキーが誕生した当初の古典的な製法を、現代のウイスキーづくりに復活させた世界的にも希少な設備です。
スコットランド製ポットスティルに国内のピザ窯職人による竈を組み合わせた独自の設備。技術革新であるだけでなく、唯一無二の風味づくりも実現しています。

SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を
地元の森林管理や地域との協働
薪を活用するにあたり、地域の林業関係者や木こりたちと協働し、持続可能な森林管理の一翼を担っています。
手入れされない森では、倒木がそのまま腐敗し、強力な温室効果ガスであるメタンガスを発生させることがあります。
一方で、間伐材を燃やすことで出る二酸化炭素は、木が成長の過程で吸収した炭素を大気に戻すだけ。これは「カーボンニュートラル」なサイクルとされ、地球環境への負荷が比較的小さいと評価されています。
この取り組みは、地元の森の健全な循環(里山再生)と、気候変動への地域レベルでの適応・緩和の両面で意義のあるものです。
廃棄物のリサイクルと環境配慮



SDGs目標12:つくる責任 つかう責任
「製造」 だけで終わらない、循環型ウイスキーづくり
製造過程で発生する残渣(ドラフ)は、地元の脱水機メーカーと手を組み、クラフトウイスキー業界でいち早く、地域の畜産の飼料とするシステムを開発。資源循環として地域との共生を実現しています。さらにドラフを圧縮したコースターなどの独創的なグッズも展開。
また、蒸溜所で役目を終えた樽材などの資材も可能な限りリユース。ウイスキーボトルのディスプレイ什器など、様々な形で再利用の可能性を模索しています。

SDGs目標6:安全な水とトイレを世界中に
「生命の水」を守る、責任ある排水管理
ウイスキーづくりには大量の水が必要ですが、静岡蒸溜所では、製造工程で使用した水をしっかりと浄化して美しい河川に戻しています。また、栄養豊富な蒸留廃液については飼料化を実現しています。
また、温水を排出する際には、防火用水池に放出し、常温に下げてから河川に戻すなど、自然環境に負荷をかけないよう管理を徹底しています。
こうした日々の取り組みは「目の届くものづくり」のひとつ。水という貴重な資源に感謝し、その恩恵を未来へつなぐ努力を続けています。
地元雇用の創出、人材育成の場の提供


SDGs目標4:質の高い教育をみんなに
人を育て、街を育てる。静岡蒸溜所の挑戦
静岡蒸溜所では、ウイスキーづくりを軸に、地域の人々が学び・働き・つながる機会を数多く創出しています。
一般向けに開講している「ウイスキースクール」では、製造工程を学びながらウイスキー文化への理解を深めることができ、全国各地から地域の住民まで、貴重な学びの場となっています。
また地元大学と連携し、起業や地域活性化をテーマとした講義・交流の機会も設けるなど、幅広い世代に開かれた学びの場を提供しています。
さらに、「静岡をウイスキーの街に」という大きなビジョンのもと、地域内でのウイスキーイベントの開催にも取り組んでいます。
蒸溜所が起点となり、人・知識・経済をつなぐ循環が、静岡の新たな魅力を生み出しつつあります。
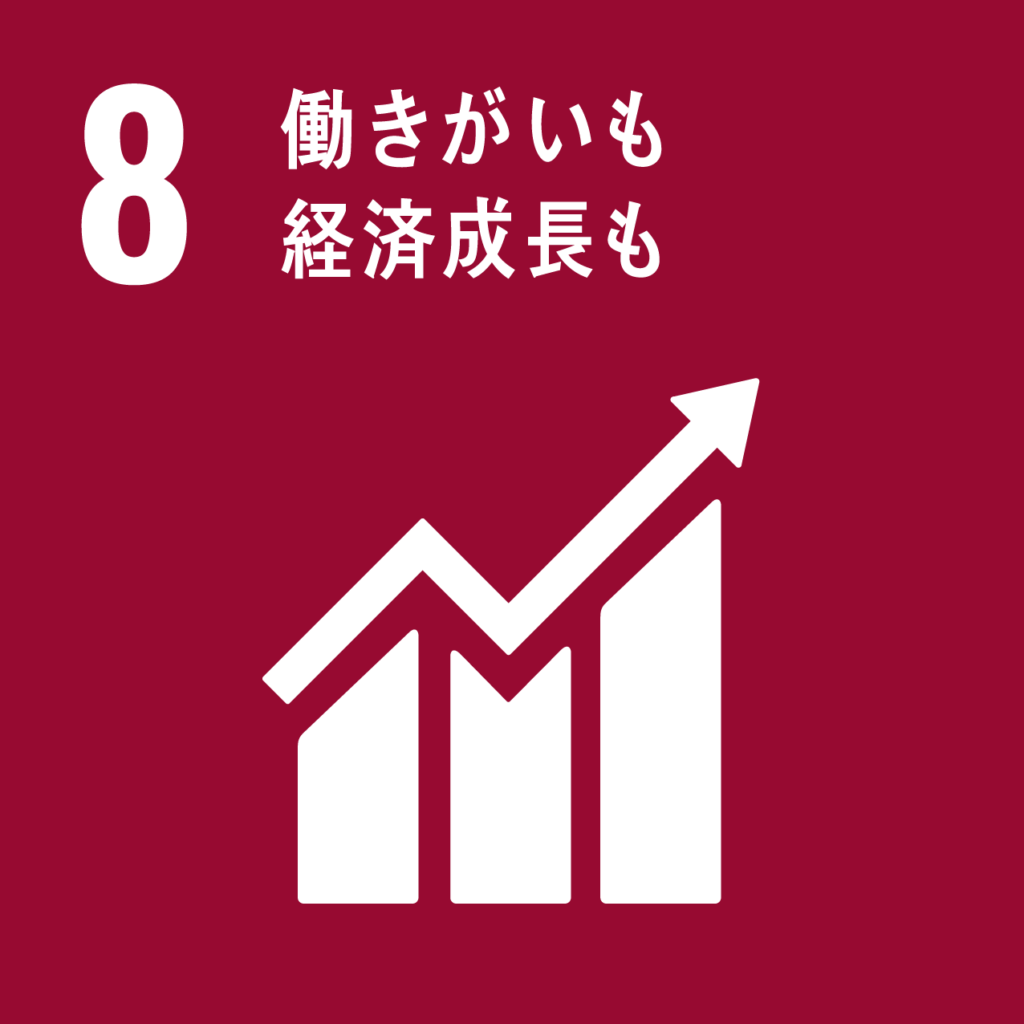
SDGs目標8:働きがいも経済成長も
「つくる人も輝く蒸溜所」へ。
雇用面では、地元人材の積極採用に取り組みつつ、全国から魅力を感じて集まる若者が市内に居を構えることで、街の活性化に貢献。静岡の地で働きがいを感じられる職場環境づくりを推進しています。
さらに、スタッフの国内外での研修を定期的に実施し、ウイスキーづくりの知識と技術の向上、そして仕事への誇りややりがいの醸成を目指しています。
こうした人材育成の取り組みは、社員一人ひとりの成長を通じて、地域経済の発展にもつながっています。
国内外とのパートナーシップ構築


SDGs目標17:パートナーシップで目標を達成しよう
ウイスキーで地域と世界を結ぶ
静岡蒸溜所のウイスキーづくりは、多くのパートナーとの協働によって成り立っています。
地元の農家と連携した県産大麦の使用、地域の木材業者と進める薪の調達と森林整備、さらには地元大学・研究機関との知見の共有など、地域資源と知恵を活かした取り組みは、まさに「地域との共創」。
一方で、海外との関係も大切にしています。
持続可能な輸出体制の構築を目指し、海外市場との健全な関係を維持しながら、日本発のウイスキーの魅力を世界へ発信。さらに、海外の優れた製品や技術を柔軟に取り入れ、国際的なウイスキー専門家との協業も進めることで、品質と表現の幅を広げています。
地域と世界をつなぐ懸け橋として、今後もパートナーシップの力で、より良いウイスキーづくりと持続可能な未来の両立を目指します。
上記のような、地域に根ざしたサステナブルな活動を継続している静岡蒸溜所。
今回の受賞は、こうした私たちの地道な取り組みが、ウイスキー業界関係者のみなさまに評価されたものと受け止めています。
「持続可能な蒸溜所」であり続けるために。ウイスキーづくりには、長い年月と自然の恵みが欠かせません。
だからこそ、自然と調和し、地域と共に成長していく仕組みを築くことが、静岡蒸溜所の目指すウイスキーづくりの根幹です。
これからも一歩ずつ丁寧に歩みを進めてまいります。今後も静岡蒸溜所への応援をよろしくお願いいたします!
※この受賞の詳細は、TWSC2025公式ウェブサイトでもご覧いただけます。